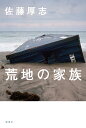佐藤厚志『荒地の家族』
久しぶりに真っ当な、ストレートな、小説らしい小説を読んだ。
第168回芥川賞受賞作。舞台は仙台市の沿岸にある荒浜地区。東日本大震災発生時、いち早く速報が流された地だ。その内容は「200~300人の遺体を発見か」というものだった。あの大惨事から十年。著者は、荒浜で造園業を営む四十男を主人公に据え、被災地で暮らす人々の日常を、抑制した筆致で描いていく。
しかしその「日常」のなかには、憤怒や諦め、やるせなさといった様々な感情が渦巻いている。震災という理不尽で圧倒的な暴力の前では、その感情を向ける先がない。そうした言葉に言い表せない被災者の心のうちを、著者は「身体」と「精神」のズレのようなものを執拗に重ねていくことで表現していく。その筆さばき、言葉の選び方が絶妙で、巧い。
個人的に感じ入った場面を引く。場所は新築家屋の庭。祐治というのが主人公の男。晴海は震災後に急逝した元妻、知加子は流産ののち、今は別居している再婚相手。啓太は男のひとり息子だ。
〈 新築家屋の壁を背にして祐治は石を積んでいた。現場は海に近かった。定年近い施主夫婦は広い庭が欲しくて亘理に家を建てたという。畑や更地が辺りを占めていたが、ぽつぽつと新築の家屋が建っていた。
積む石を選んでいると、晴海や知加子の腹の中で成長を止めた子を思った。浮かんでは消える想念に祐治はこだわらなかった。死んだ人間に寄りかかっていたら、自分も半死半生だと思った。それでも何度も立ち止まって死者を思い、自分に何ができて何ができなかったかを考えてやりきれなくなる。人を思い出す時、ひと続きの記憶が現れるわけではない。そのときに味わった感情、手触り、痛み、苦しさが点々として残りかすのようにあるだけだった。
俺にしても死ぬ順番を待つ大行列のひとりに過ぎない。生きている間にどうにか飯を食って啓太を育てるだけだ。
背中に当たる午後の強烈な日差しが暑く、全身に汗が滲んだ。石を載せたビニールシートから高温で溶けたプラスチックのような臭いが漂ってくる。梅雨の前で湿気はなく、乾いていた。 〉
男の石積みは、どこか賽の河原での「苦行」を思い起こさせる。肉体的にも精神的にも、大きな痛みをともなう苦行だ。男だけではない。物語に登場する被災地で生きる人々の多くが、歯噛みしつつも「苦行」を受け入れ、はた目には淡々と生きようとしている。そんな人たちと交流を持ちつつ、男は絶えず「動く」こと、働くことで、その苦行を少しでもやわらげようともがく。
理不尽な状況の中で砂を嚙む思いで生きる人は、何も被災地に限ったことではない。いまや日本のあちこちにいる。この物語の特徴は、震災を描きつつも「震災の悲劇」に留まっていない点である。例えばクッツェーの『鉄の時代』のように、大きな普遍性を孕んでいるのだ。その源泉は、言葉に対する著者の、圧倒的なまでの信頼感にある。そしてその言葉を丁寧に積み重ねていく繊細さに由来する。
久しぶりに真っ当な、ストレートな、小説らしい小説を読んだ。そんな思いがした。